長く使い続けられる建築をつくる
(NASCA)
建築家としてさまざまな作品やプロジェクトを手掛け、大学での研究・教育も精力的に続けてこられた古谷誠章さん。建築職能団体でも重責を務めています。ホームページにはキーワードが散りばめられ、それらが関連し合い、Shuffledされて新たな出会いが生まれるという古谷さんの建築観を表現しているかのようです。設計された作品をもとにお話をうかがいました。
建築家としてさまざまな作品やプロジェクトを手掛け、大学での研究・教育も精力的に続けてこられた古谷誠章さん。建築職能団体でも重責を務めています。ホームページにはキーワードが散りばめられ、それらが関連し合い、Shuffledされて新たな出会いが生まれるという古谷さんの建築観を表現しているかのようです。設計された作品をもとにお話をうかがいました。
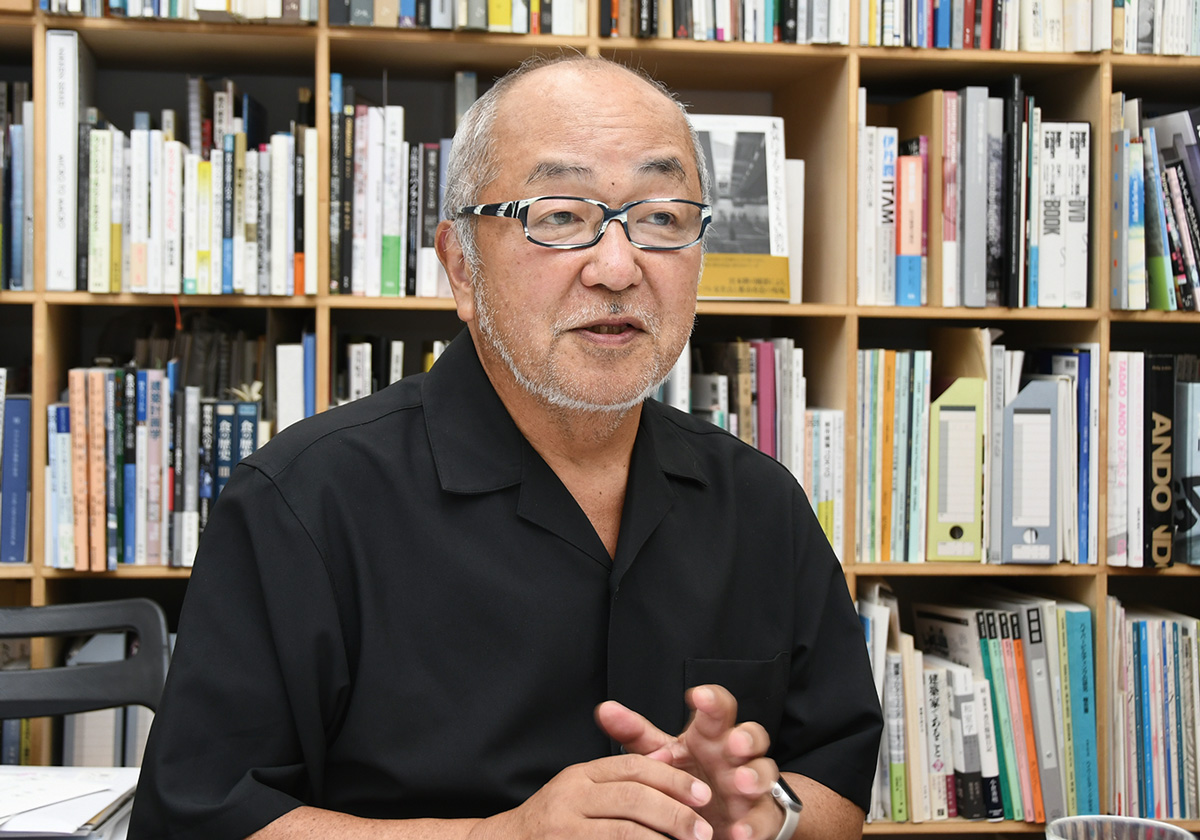
——大学での建築教育と建築家という実践を長年続けられました。どのような考えがもとになっていますか。
私の大学時代の恩師は穂積信夫先生で、修士の時から関わったのが「早稲田大学本庄高等学院」の設計です。その後助手として研究室に残り、大学にいながら設計をするという環境の中で育ちました。本庄高等学院は、日本でほとんど最初の本格的な教科教室型(普通教室がなく英数国理社が別棟)の高校です。こういう発想は、教育研究の活動と実践する設計の場が掛け合わさらないとできないもので、自分自身のやり方の原点でもあります。
学生にとっては教科書だけで設計を教わるより、建築家から教わることでリアリティのある教育を受けることができます。教員の私にとっては学生に示せる教材となるような建築をつくり続ける必要があり、私自身の気持ちを高めることにもなります。それが建築家としても設計を続ける大きな原動力となりました。
——設計においてワークショップを大切にされています。
本庄高等学院で、これまでにない教科教室型の教育の場をつくろうとした結果、使う側の先生からは戸惑いの声がありました。見たことも聞いたこともない校舎をいきなり操縦しろと言われても、やり方がわからないということです。ユーザーが設計プロセスの段階から参加して、一緒につくり上げることの重要性を感じました。
同1995年にコンペで2等になった「せんだいメディアテーク」では、まさにShuffledされた図書館を提案しました。しかし、それをいきなり渡してもうまくいかないので、提出したレポートの後半は、どうやって図書館員やユーザー、子どもたちを含めてワークショップをするかについて記述しました。
同時期に設計した高知県の「アンパンマンミュージアム」では7分の1の模型を現場につくり、子どもたちとワークショップやイベントをして、本物ができる前に予行演習をしました。それにより、将来の利用者が具体的な使い方をイメージするのに役立ちました。ミュージアムを実際に使える日を子どもたちも楽しみにしていました。これが私の最初のワークショップです。
ワークショップが本格化したのが「 神流町 合同中里庁舎」です。ここは役場の建て替えでしたが、早晩には役場でなくなることが予想されたので、そうなった時にどうするかをテーマに小中学生と一緒に考えました。それを間接的に見ている大人や職員も、どうすればよいか考える機会になりました。引き渡しの翌日には合併することになり、役場としての建物ではなくなりましたが、将来の変化への準備ができていたため、多機能な施設として第二の人生を歩んでいます。
「茅野市民館」は設計者を選ぶプロポーザルがすべて公開されました。熱心な市民の方たちは、プロポーザルで何が評価されたのかも一緒に聞いていました。選んでいただいた私は、市と市民との協働の場である基本計画策定委員会に招集され、開館準備期間までの5年間にワークショップを143回開催しました。
ワークショップでみんなの意見を受け入れるあまり、最初の案から離れたものになりそうになることもありました。そうすると、「プロポーザルでの古谷さんの案の良かったところがなくなるようなことはするべきではない」と、市民の方々が戻してくれたのです。それもワークショップの大きな効用でした。

茅野市民館(2005)
Photo:淺川敏
——「氷見市芸術文化館」はとても開放的な外観ですね。
「氷見市芸術文化館」は、設計にかかった途端に富山県全域のハザードマップが見直され、この地域の浸水リスクが50cmから最大5mに大幅に上昇したため、ホールの主要機能をすべてピロティで持ち上げることになりました。これにより館自体が浸水から免れるとともに、地域の人たちの避難場所にもなります。そのためにも「あそこに行けば大丈夫」と分かる外観にしたい。さらに、文化館には回廊や広場、外部階段を設けることで、近隣の学生にとっても放課後を過ごすサードプレイスになればと思いました。そこで、市民が日常も非常時もここに集まることができる、出入り自由な場になることを考えました。
ホールや劇場は、中でイベントが行われても閉まっていたら外の人にとっては何もやっていないのと同じです。それが半開きや全開することができると、中の市民の活動が見えるようになります。それはすごく大事なことだと思っています。開いている箱を閉ざすことは簡単ですが、閉じてつくった箱は開けられません。だからこのホールは、閉鎖的ではなく「開けられる」状態でつくられており、内部の活動が外部から見えることで市民の関心をひき、新たな参加の機会を促す意図があります。

氷見市芸術文化館(2022)
Photo:淺川敏
——「鹿島市民文化ホール」はホール内外がループ状につながっています。
「鹿島市民文化ホール」は、地元の小中学生や音楽の愛好団体など、普段の練習にも本番でも使えるような市民のためのホールです。 下見に行ったときに、中学生がコンサート後に表にまわってお客さんのお見送りをしていました。それを見た瞬間にピンと来て、館の内も外もグルグル回ることが自然にできるホールにしたいと思ったのです。
コンサートなどで今まで客席にいた人たちが、次には舞台で演奏し、また客席に戻るといった、舞台と客席をグルグル回れるようにするため、館内もループ状につながっています。

鹿島市民文化ホール(2023)
Photo:淺川敏
——金属屋根については、どのような印象がありますか。
傾斜屋根にするときは金属屋根を使うことが多いです。小布施の町立図書館「まちとしょテラソ」は三角形が麦わら帽子をかぶったような形で、金属屋根を使っています。最近では岩手県の田野畑村の木造の「道の駅たのはた」も金属屋根です。木造とは相性がいいし、耐候性もありますね。
ステンレスの場合は、さらに色の展開があるといいですね。
——ご多忙のなか、建築職能団体の会長職も歴任されています。
建築職能団体での仕事では、次世代の建築家が活躍できるような社会や環境をつくりたいと思っています。障壁はありますが、それらを1つずつよくしていきたいと設計者選定の方式や、海外の仕事ができるように国際的にも通用する資格をつくる取り組みも行っています。
次世代だけでなく、今、全国の建築家が抱えている問題も含めて、建築家が仕事を継続できる環境をつくっていく。環境を整備できれば、人びとの生活環境の向上につながると考えています。
誰しも建築がつくり出す生活環境におかれています。今後も、建築が維持・管理されて使い続けられる社会を実現できるよう取り組んでいきたいですね。
——ありがとうございました。
古谷誠章(ふるや・のぶあき)
1955 東京生まれ。1978年 早稲田大学理工学部建築学科卒業。1980年 早稲田大学大学院修了。1986年 近畿大学工学部講師。1994年 早稲田大学理工学部 助教授。1994年 八木佐千子と共同してNASCAを設立。1997年 早稲田大学理工学部 教授。2017年 日本建築学会 会長。2020年 早稲田大学芸術学校 校長。2021年 東京建築士会 会長。2024年 日本建築士会連合会 会長。