社会や文化に受け入れられる建築を考える
東京工業大学での建築教育とともに、アトリエでは大学施設や駅舎の設計など、多くの人に親しまれる建築を数多く手がけています。
今回、これまでに設計された美術館を中心に、建築や環境に対しての考えをうかがいました。
東京工業大学での建築教育とともに、アトリエでは大学施設や駅舎の設計など、多くの人に親しまれる建築を数多く手がけています。
今回、これまでに設計された美術館を中心に、建築や環境に対しての考えをうかがいました。
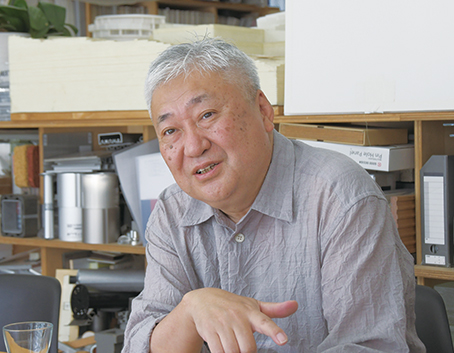
——建築めざすきっかけや大学時代のことを教えてください。
高校3年生になって大学進学のことを考えているときに、TVコマーシャルで清家清先生が図面を描いている姿を見て、建築は面白そうだと思いました。それで先生がいる東京工業大学の建築学科を受けることにしたのです(笑)。
当時、清家先生はほとんど授業に来られることがありませんでした。ところが先生が定年される前年、私が大学2年の時は、建築意匠の授業に先生が何度か来られたのです。直接先生から教えていただけるのは稀なため、貴重な授業を受けることができました。
4年からは篠原一男先生の研究室へ。当時、篠原先生は「上原通りの住宅」等次々に話題作を発表していました。先生からは教わるというより、設計している姿を後ろから見るだけでしたが、修士1年の時に声をかけていただき、住宅の設計を手伝うことができました。
——大学院修了後日建設計に入社されますが、環境は変わりましたか?
篠原研では主に住宅を設計していたので、大きい建築をつくるチャンスが欲しかったのです。その頃『SD別冊 日建設計林グループの軌跡』という雑誌を古本屋で見つけて面白そうだと思い、日建設計(以下「日建」)への進路について篠原先生に相談しました。実は林さんと篠原先生は、清家先生の研究室の同級生だったのです。日建の面接は1度きり、当時副社長だった林さんに図面を見ていただき、入社することになりました。
その頃、日建では10年目くらいの先輩が若手に建築の設計プロセス全般、計画・設計・監理を満遍なく体験できるように、3〜5年かけて育成してくれました。それはとてもありがたかったですね。
僕がまだ新人のときに、上層部から何をやりたいのか聞かれ「美術館をやりたい」と言ったところ、「練馬区立美術館」の実施設計をお手伝いすることになりました。美術館は建築家にとって携わりたい建築の一つなので、ラッキーでした。
——「ポーラ美術館」の設計もされました。
日建時代に丸4年休職してアメリカに行っていました。ヨーロッパなどの旅先では都市でも田舎でも美術館が必ずあり、時間があると必ず見てまわっていました。東京に戻って1年くらいした頃、「ポーラ美術館」の設計を担当することになりました。林さんは担当者を決めるに際して、「余計な経験があると新しいアイデアが生まれてこない」「30代の若い人」という考えのようでした。僕が31歳のときです。チームで設計が始まって「形」ができたのが34歳頃でした。国立公園内の森に建つため、お役所との交渉に5年くらい費やしました。
——森の中に溶け込むような形はどのようにして生まれたのでしょうか。
設計に入る前に、森の中に建つ建築・美術館とはどうあるべきかについて、林さんのオフィスに各担当者が週に1回くらい集まって、ディスカッションを続けました。丸テーブルを皆で囲み、絵を描いていたら建築が丸くなりました。森の中で最小限切り取って、あとは触らない。その形が円形でした。円はヒエラルキーがなく、全方位に対して優劣のないように。森に対しても人に対しても同じように公平に扱うという考え方です。
——2002年に独立されますね。
「ポーラ美術館」の竣工日が2002年9月7日。月末に日建を離れて10月1日から東京工業大学で教えることになりました。事務所を開設したのは数か月後です。
独立後は日建時代と違って、外部の構造・設備エンジニア達とチームを組みますが、モノをつくるのに組織の内の人、外の人という境界はありませんでした。お世話になりっぱなしのメーカーの方々にも独立したことを連絡しましたが、日建時代と同じように接してもらいました。

ポーラ美術館(2002)
写真撮影:石黒 守
——京都の名勝地・嵐山に設計された「福田美術館」について教えてください。
施主は「ポーラ美術館」を見て来られ、「美術館の内と外を一体化する」というテーマをお持ちでした。敷地からは嵐山や大堰川などの豊かな大自然の風景が広がっています。新参者がこの“場”にどう根を下ろすか、そこが重要です。
美術館が森にあろうが都市にあろうが、僕の意識では同じです。箱根では森を、嵐山では川岸の街を改変していく。その作法は違いますが、根本に流れる精神はまったく同じ。どちらも周辺の環境に最大限敬意をはらって、どうやってここの土地に馴染んでいくか、あるいは入れていただくかということです。
「福田美術館」では周辺の住民だけでなく、街に対してのみならず、1200年の長い歴史の中でこの建物をどのように受け入れていただくかをずっと考えていました。
——金属屋根についてどのようにお考えでしょう。
京都嵯峨嵐山地区は景観の規制があり、屋根材の基本は銀鼠の日本瓦です。「福田美術館」は屋根を瀟洒に仕上げたいので金属がふさわしいと思いましたが、基本的に金属だけでは受け入れられないのです。そこで瓦棒部分を銀鼠の陶器にすることで許可をいただきました。
金属屋根というとスパンを飛ばし、工場、駅舎の屋根など工業的なイメージがあります。「福田美術館」では、古都の風景の中でも金属屋根を使えることを実証したかった。三晃さんの仕様ではなかったんですけどね。京都らしさに敬意を払いながら、建築がつくられる時代時代を反映し、特有の表情が出てくるべきだと思います。
——最後に、仕事や大学教育について考えていることを教えてください。
設計はスパンが長いです。「ポーラ美術館」は10年、「福田美術館」も15年。今関わっているプロジェクトも完成まで最低10年かかります。
社会に貢献できる建築は長いスパンで建っているので、やはりそれなりの時間をかけて、その風景に溶け込めるか、社会やその土地の文化に対して建築が受け入れられるかをいつも熟考しています。それが設計の行為なのかと最近考えます。
もう一つは後輩との関係です。先ほどもお話ししたように、先輩からいろいろ教えていただき受け継いできました。それを次の世代に渡していきたい。大学教育も設計事務所も同じです。若い人を育てて、自分も成長する。そういう未来の人たちへの伝言をやっていかなければいけない、それはある意味宿命です。
いろんな人に恩を受けましたからね。
——ありがとうございました。

福田美術館(2019)
写真撮影:石黒 守
安田幸一(やすだ・こういち)
1981年 東京工業大学工学部建築学科卒業。1983年 東京工業大学大学院建築学専攻修士課程修了。1983〜2002年 日建設計。1989年 イェール大学大学院建築学部修士課程修了。1988〜91年 バーナード・チュミ・アーキテクツ・ニューヨーク事務所。2002年〜現在 東京工業大学大学院教授、安田アトリエ主宰